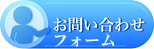下記のように私たち土地家屋調査士へのご相談は多岐にわたります。
土地編 目次
Q2 登記面積と実際の敷地の面積とに食い違いがある場合、その原因とは?
Q3 境界の立会いは何のためにするのか?
Q4 境のしるしにはどんなものがあるか?
Q5 法務局にある「公図」はどの程度あてになるものなのか?
「地積測量図」は測量の図面だが、そもそも誰がどのようにつくっているのか?
Q6 現況測量と境界確認測量(確定測量)の違いは?
Q7 兄弟共有(持分 各2分の1)の土地を2つに分けたい場合、どういう段取りになるか?
Q8 相続した土地が登記上は「畑」だが、もう20年も家が建っている土地。地目を「宅地」に変更できるのか?
Q9 越境するものとして、具体的に何があるか?そもそも、越境しているとはどういう判断か?
Q10 国有地(青地など)の払下げ手続きは、一般的にどのぐらいの手続きと期間がかかるのか?
Q11 なぜ、道路と自分の土地との境を確定しなければならないのか?
建物編 目次
Q2 建物工事がどの程度進めば、新築建物として表題登記を申請できるのか?
Q3 登記できる建物と登記できない建物とは?
Q4 建物登記の床面積に算入されるもの、されないものは何か?
Q5 建物を未登記にしたままにしていたら、どのようなメリットがあるか?
実際には2階建てなのに、1階建てのままの登記にしていたらどうか?
Q6 建物を登記するにあたり、所有権を証明する書面として添付するものは具体的に何か?
Q7 書類不足の建物登記の例(築80年で大工さんすら分からない場合、登記できるのか?)
Q8 自分の土地は更地なのに、知らない人の古い建物の登記が残っていることが分かった。解消できるのか?
Q9 3人で共有の建物を取り壊した場合、その共有者の1人から建物を壊したと滅失登記を申請できるのか?(原則)
Q10 普通の一戸建て二世帯住宅は、区分建物として登記できるのか?
Q11 店舗併用住宅の登記で注意することは?
【土地編】Q1 土地の登記資料の、基本的な調査はどうやるのか?
登記資料は法務局という国の出先機関にあります。
そこで「公図」「登記事項証明書」「地積測量図」を取得することができます。
ただし、土地のすべてに「地積測量図」が備えられてはいません。
また、「公図」の形が現在の利用状況と違っている場合があります。
現在の「公図」以外に、昔の公図である「旧公図」が取れることがあり、かなり古い時代の土地の形がわかる資料もございます。
法務局以外では、市役所に「道路査定図」という道路の図面があり、これも重要な資料の一つです。
【土地編】目次に戻る
【土地編】Q2 登記面積と実際の敷地の面積とに食い違いがある場合、その原因とは?
法務局に「地積測量図」がない場合、土地の境が不明確なまま現在に至っているのかもしれません。
そのため、こんにち「境界確認測量」をすると、周囲の土地所有者様全員と立会いをすることで、自分の土地の形と広さがはじめてはっきり分かります。
その際、登記面積と実際の面積とで、大なり小なり相違が出てくると思います。
そういうわけで、原因は例えば
(1)今までずっと境が不明瞭だった、測量をしたことがない
(2)地積測量図が備え付けられているが、古い図面のため、不正確なことがある
(3)他人の土地の範囲まで、自分の土地と勘違いをしていて今日まで利用している
など、いろんな原因があります。
【土地編】目次に戻る
【土地編】Q3 境界の立会いは何のためにするのか?
そもそも、日本の土地の約半分ぐらいしか、法務局という役所の公的な資料「地積測量図」が備え付けられていません。
また、現場を見てみると、土地の四隅の全部に土地境のしるしが存在していることも少ないのです。
だから、土地について「どこからどこまでが自分の土地か」を明確にする必要があります。「家を新築したが、隣に屋根が飛び出している(越境している)とクレームを受けた」、「土地を売却したいが、買主に土地の範囲がどこまでかと説明ができない」など、土地境について、様々な問題がございます。
そこで
(1)資料収集
(2)実地を測量して、土地境を研究する
(3)周囲の土地全員の所有者様に立会いをして説明する
(4)境のしるしの無いところに境界を設置し、周囲の土地全員の所有者様に写真や図面などをお渡しする
などの作業をします。
【土地編】目次に戻る
【土地編】Q4 境のしるしにはどんなものがあるか?
石杭、プレート、鋲、赤ペンキ、キザミ、プラスチック杭、公共の石杭、公共プレート、境の木、構造物、ブロック角、鉄パイプ、木の幹にピンクのリボンのリボンなど
それぞれにそれぞれの意味があります。
【土地編】目次に戻る
【土地編】Q5 法務局にある「公図」はどの程度あてになるものなのか?
「地積測量図」は測量の図面だが、そもそも誰がどのようにつくっているのか?
「公図」はそれぞれの土地がどの位置にあるか、どのような形か、などを示す図面です。見取り図のようなものです。
この「公図」にあらわされている「ご自分の土地」が「形が違う(四角形なのに五角形)」、「広さが隣の土地と比べて狭すぎる」、「同じ法務局で取得できる地積測量図という資料と、形や広さや位置が矛盾している」ということがあります。
なお、「地積測量図」という法務局備え付けの図面資料は、我々土地家屋調査士が測量し、立会いをした上で作成します。
その図面を添付して「土地地積更正登記」(土地の広さを正確なものに直す登記)や「土地分筆登記」(一つの土地を複数に分ける登記)などを申請します。すると、それを法務局が備え付けます。
【土地編】目次に戻る
【土地編】Q6 現況測量と境界確認測量(確定測量)の違いは?
現況測量…
境界標・ブロック、既存建物の角、電柱、道路、U字溝、高さなどのありていを測って、現地の形状や面積を示す図面を作成することで、境をお隣と立会いしたり確認するわけではない測量です。
境界確認測量・境界確定測量・確定測量…
お隣と土地の境を確認した後、図面を取り交わします。土地地積更正登記を申請するときに利用する図面でもあります。
土地地積更正登記や分筆登記を申請する時に、地積測量図を添付して申請しますが、申請するつど法務局が備え付けていきます。
その後この図面は、法務局で誰でもが申請して見ることができる図面となります。
有効な境界確定測量をしたから、地積測量図を作成することができるのです。
【土地編】目次に戻る
【土地編】Q7 兄弟共有(持分 各2分の1)の土地を2つに分けたい場合、どういう段取りになるか?
大原則として、土地を分ける場合、その土地の外枠の境がはっきりしていないと、土地分筆登記申請は通りません。
「外枠の境」とは、その土地の外周が確定している(周囲の土地所有者全員がそれを認めている)ということです。
そして、分筆登記を申請しますが、どういう形に分けるのか、左右どちらの土地をどちらの土地にするのかなど、打ち合わせをしながら慎重に行います。
なお、土地を2つに分けただけでは、共有の土地が2つできあがるだけです。そのため、個々の土地を完全に1人名義にするために、分筆の次は司法書士先生に所有権の持分の移転の登記を依頼する必要があります。
【土地編】目次に戻る
【土地編】Q8 相続した土地が登記上は「畑」だが、もう20年も家が建っている土地。
地目を「宅地」に変更できるのか?
登記事項証明書の地目欄について、明らかに現状利用と登記地目が異なっている場合があります。
この場合、我々が調査をして、法務局に「土地地目変更登記」を申請します。
【土地編】目次に戻る
【土地編】Q9 越境するものとして、具体的に何があるか?
そもそも、越境しているとはどういう判断か?
軒、雨どい、屋根、下水管、水道管、下水枡、室外機、物置などがよくある事例です。
しかし「越境」と言っても、そもそも「正しい境はどこか」と境界を先に決めることをしないと、何がどのぐらい越境しているのかが分かりません。そこで、越境問題の正しい解決方法とは、境をはっきりさせるという作業を先に行うことがポイントになると思います。
【土地編】目次に戻る
【土地編】Q10 国有地(青地など)の払下げ手続きは、一般的にどのぐらいの手続きと期間がかかるのか?
自分の敷地内に国有地(青地)があって、家を建て直すのに支障がある場合。
その土地を国から買うことで、問題を解消することができます。
そもそも、国の土地を買うことができるのか、個別的に様々な前提があるため、その調査から始めます。国から土地の払下げを受けること、国有地との境界を確定すること、国道との境を確定する、など国との境界確定にはかなり時間がかかることが多いです。
また、そのために現地の測量データを作成して打ち合わせをするため、資料集めだけではなく測量作業が必要になります。
はっきりした時間は断言はできませんが、非常に繊細な作業を行うことが重要です。
【土地編】目次に戻る
【土地編】Q11 なぜ、道路と自分の土地との境を確定しなければならないのか?
土地の境をお隣の方と立ち会ってはっきりさせる測量作業を「境界の確定測量(=境界確認測量)」といっていますが、私有地同士の境のラインだけではなく、道路との境のラインも定めないと、自分の土地を囲むことができません。「全周囲」が決まってはじめて、自分の土地の形と広さがはっきりわかります。
「道路はさすがに公共のものだから、正確に形や長さが決まっているはずだ」と思われがちですが、現実にはむしろ逆です。「自分の土地と道路との境が厳密にはっきりしていない」ことは多いです。
自分の土地は確かに公道(国道や県道や市道など)に面しているが、どこまでが自分の土地なのか境目が分からない、ということです。それを「未査定道路」といいます。逆に、境目がはっきりとしている場合は「査定済道路」といいます。
「土地地積更正登記(土地の面積や形を正しく登記し直す。権利証である登記識別情報の数値が変わる)」を申請する場合や、「土地分筆登記(土地を複数に切る)」を申請する場合には、お隣の方全員との土地境をはっきりさせることは当然として、加えて道路との境をはっきりさせなければなりません。
その分、役所との打ち合わせや手続きが加わるので、費用も期間も加わります。
【土地編】目次に戻る
【建物編】Q1 建物を新築したときは、どのような登記をするのか?
まず、土地家屋調査士が現地を確認して申請書と図面をつくり、建物の表題登記申請を行います。
そして、法務局が受理して書類や現地を検討し、登記データをつくります。
例えば、「鎌倉市大町10番地、居宅、木造スレートぶき3階建、床面積 1階、2階、3階 すべて30㎡、家屋番号(家の名前)10番」と登記されます。
その上で司法書士背根氏が権利(保存)の登記申請を行います。
この二つの登記は同時に出せず、一つ終わったら次、という順序です。
【建物編】目次に戻る
【建物編】Q2 建物工事がどの程度進めば、新築建物として表題登記を申請できるのか?
新築建物の施主様の入居や銀行ローンの都合、工事人への支払い時期の都合で、「建物表題登記」の申請や完了時期が大切なことが多いです。
慣れていない住宅メーカー担当者や不動産仲介業者の中には、「登記はなんでも司法書士が行うものだと誤解して、建物表題登記を一旦しないと司法書士先生による権利登記ができないことを知らない、銀行の抵当権設定ができないから銀行の融資が実行されない。そのため、決済や引き渡しができないためトラブルになる」というケースがございます。
簡単に言えば、「建物が物理的に完成してから表題登記の申請ができる。完成していないものに、できました、とは申請はできない」ということです。では、「建物はどういう状態になったら完成したと言えるのか」?
それは壁や屋根、窓やドアがついていて、内部に床があり、照明やトイレ、お風呂、給排水の設備など内部設備工事が完了している状態が「建物が完成している状態」といえます。
ただし、各部屋の内装クロスの仕上げ作業が途中だったり、押し入れの建具が一部ついていなかったり、工事の面から足場パイフがまだ残っているなど、現実の現場では色々なケースがあります。
【建物編】目次に戻る
【建物編】Q3 登記できる建物と登記できない建物とは?
登記すべき建物、登記できる建物とはどういうものかというと、下記のような性質のある建物をいいます。
〇外気と完全に分断されている(野ざらしの自転車置き場は屋根がついているだけでは、外壁で囲まれているわけではないため×)
〇用途性がある(建物らしい外観はあっても、トイレもお風呂もなく、水道も電気も通っていない、まるで生活できない…では×)
〇地面にしっかり定着している(仮のプレハブ物置で、かんたんに動かせるものは×)
〇構築性がある(自然にできた洞窟のほら穴にカーテンをつけた、では×)
〇住宅なら人がきちんと住める、倉庫なら物を保管できる、というように用途・目的を達成する性質があること
このような性質から考えてみると、登記できる建物、できない建物の例が下記にあげられる(例外もある)。
× メリーゴーランド
× 農業用のビニールハウス
× 寺院の鐘楼(鐘つきのための工作物)
× ガソリンスタンドの給油部分
× 鎌倉の大仏(内部に入れるが、内部を利用するための設備などはないため用途性を欠く)
〇 大船の観音(内部に祭壇が設けられていて、寺院本堂として利用しているので用途性がある)
〇 打ちっぱなしのゴルフ場
〇 農業用のガラスハウスで耐久性があるもの
〇 東京ドーム(屋根は空気膜屋根と表示されている)
〇 JRガード下の新橋の飲み屋(木造ガード下平家建)
〇 駅舎
〇 戦艦三笠(記念館)
〇 シンデレラ城(ディズニーランド)
〇 スプラッシュ・マウンテン(ディスニーランド)
〇 東京タワー(電波塔・店舗・事務所)
【建物編】目次に戻る
【建物編】Q4 建物登記の床面積に算入されるもの、されないものは何か?
× ベランダ、テラスは外気分断性がないので、床面積に算入しない
〇 小屋裏収納スペースは天井高が原則1.5㎡以上ある場合、床面積に入れる。ただし、小屋裏収納の天井高は低かったり高かったりすることが多く、個別では検討となる(例 斜めになっている勾配天井)
〇 出窓のうち、床と同じ高さで、高さ1.5㎡以上のものは床面積に含む。そうでない場合は含まない。
〇 堅固なサンルーム
〇 床面積の算入、不算入については個別性があるため、現地調査して検討することになる。面積の大小は、銀行融資を受けられる、受け入られない、に影響することも多い
【建物編】目次に戻る
【建物編】Q5 建物を未登記にしたままにしていたら、どのようなメリットがあるか?
実際には2階建てなのに、1階建てのままの登記にしていたらどうか?
増築した2階部分は、1階部分の工事費を出資した人と同じかどうかはっきりしない。
(例 あとから増築した2階部分は、自分の弟が出資した、おじさんが出資してつくった、兄弟4人で共同でお金を出した、など)
この場合、現実の建物を正しく登記されていないと、これを担保に抵当権を設定することが危険なので、銀行からの融資ができません。また、土地建物の売買について、その時点でやっと正しく登記手続きをしようとしても、年月が経ちすぎて所有権を照明するものが何もなかったりします。
それならば建物を壊してしまえばよいとアドバイスする不動産担当者もいますが、その建物がまさしく他人の物であった場合はどうするのか、という問題があります。
【建物編】目次に戻る
【建物編】Q6 建物を登記するにあたり、所有権を証明する書面として添付するものは具体的に何か?
※個別性があるので参考程度です。
(1)新築したばかりの場合
・工事完了引渡証明書(施工者が建てました、渡しましたという証明書)
・確認済証 など
(2)未登記のまま30年間放置した場合
・工事完了引渡証明書
・工事代金領収書
・工事請負契約書
・確認済証
・検査済証
・固定資産税評価証明書
・上申書
・代金振り込み通帳コピー
・その頃の打ち合わせ図面 など
(3)不動産販売会社の建売住宅
この場合、A建築業者(家を建築した)から不動産販売会社へ所有権が移ったことを証するものとして
・工事完了引渡証明書
・印鑑証明書(建売業者のもの)
・資格証明書(会社謄本)
・確認済証 など
次にB不動産販売会社からお客様へ所有権が移ったことを証するものとして
・譲渡証明書(販売会社から)
・印鑑証明書(販売会社のもの)
・資格証明書(会社謄本) など
【建物編】目次に戻る
【建物編】Q7 書類不足の建物登記の例(築80年で大工さんすら分からない場合、登記できるのか?)
そもそも、誰がお金を出してその未登記の家を建てたのか、が重要です。
80年も前の話だとよく分からないと思われます。ましてや、どんな工務店さんや大工さんが建てたのかも分からないことが多いでしょう。当時の建築確認通知書や竣工図、請負契約書や打ち合わせ図面すらもなく、本当に自分の父や祖父が建てたものかも分からない…。
そして、もしかすると、建物建築の注文者と大工さんのような施工者との間で、その80年前に金銭支払いに関するトラブルがあったかもしれません。だから今に至って未登記だという状況は、それが本当の原因かもしれません。
このように、建物の登記申請とは難しい上に個別性があります。
解決できても時間がかかることもあります。
複雑な案件を多く解消してきた当事務所に、是非ご依頼ください!
【建物編】目次に戻る
【建物編】Q8 自分の土地は更地なのに、知らない人の古い建物の登記が残っていることが分かった。解消できるのか?
その知らない人の建物とは、例えば自分の亡父や亡祖父が昔土地を貸していて、その借主が自分名義の建物を建てた、などが考えられます。その後、土地を更地にして、返却してくれた。しかし、滅失登記(建物取り壊しを証明する登記)をすることを知らずに何十年も経った。
このようなケースでは、既に存在しない建物登記の名義人は「知らない人」ということです。
いずれにせよ、自分の土地の上に他人の建物登記が残っている場合、土地を担保に抵当権を設定したり売却したりする場合、いきなり問題が発覚して、解決できないこともありえます。
そういったことがないように、時間のある時に早めにご相談いただけることが望ましいです。
【建物編】目次に戻る
【建物編】Q9 3人で共有の建物を取り壊した場合、その共有者の1人から建物を壊したと滅失登記を申請できるのか?(原則)
原則申請できます。
国民のための法務局の資料は、明確でいつも正確であるべきものです。
建物があるとか、ないという状況は速やかに登記するようにしなければ、建物の取り違えや思わぬ犯罪を招く可能性があります。 もし建物を滅失したというのに、所有者がぐずぐすとしていて放置されてしまうと、「実際に現地に建物がないのに登記が残る」という状況になってしまいます。
建物滅失登記は、事実を報告するという性質の登記なので、共有者の誰が申請したとしても、事実が変わるわけではありません(これを報告的登記という)。別の共有者、所有者たちの利益を損ねるものではないと考えられるため、1人から申請が原則可能ということです。
しかし、その建物登記に古い抵当権が設定されている時があったり、その抵当権者を全く知らないということもございます。また、同一敷地内に似た建物が沢山あって、どれがどれだか分からないので、簡単に建物滅失登記を申請できない、ということもあるので慎重に行わなければなりません。
【建物編】目次に戻る
【建物編】Q10 普通の一戸建て二世帯住宅は、区分建物として登記できるのか?
土地は「土地分筆登記」を申請することで完全に二つに分けることができます。
相続が発生して兄弟間で一つ一つに分けたい場合には、このように分筆することが多いです。
では、建物でも「分ける」ことができるのでしょうか。
「普通建物」を「区分建物」と登記する方法がございます。
当事務所でも税理士先生から「区分建物登記」の依頼を度々受けております。
この場合、条件を満たせば可能です。
例えば、
(1)玄関、キッチン、お風呂などがそれぞれ別々でなければならない
もう片方のスペースを通り抜けて屋外に出入りすることはできない
(2)建物の中で行き来することは可能だが、扉(木製で良い)で仕切られていること
これが扉ではなく障子だと、完全に区分されているとはいえません。
このように、個別性が多い登記ですので、ご依頼いただければと思います。
【建物編】目次に戻る
【建物編】Q11 店舗併用住宅の登記で注意することは?
建物表題登記では、「居宅」「共同住宅」「倉庫」など、建物の種類を記載することになっています。
例えば、店舗併用住宅の場合、実際の利用状況が「店舗60%、居宅40%」の場合、「店舗・居宅」と表記するのが一般的です。
しかし、この時に住宅ローンでお金を借りる計画の場合、一般に100%住宅として利用する家でないと住宅ローンの融資を受けられないことがあります(事業用ローンより住宅ローンの方が金利が安く優遇されていることが多いため)。
【建物編】目次に戻る